限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)
限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)
医療機関等を受診する際に、「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」(以下、「限度額適用認定証」という。)を提示することで、提示した月の一医療機関ごとの窓口負担額が自己負担限度額までとなります。
限度額適用認定証の発行には申請が必要です。(70歳以上75歳未満の方は、所得区分によって限度額適用認定証が発行されず、申請の必要がない場合があります。)
※マイナンバーカードを保険証として利用する場合は、医療機関等での限度額適用認定証の提示は不要です。
70歳未満の方
70歳未満の方は、申請することで、すべての所得区分の方に限度額適用認定証が発行されます。
各所得区分の所得要件と自己負担限度額については以下のとおりです。
|
所得区分 |
所得要件(注1) |
|
ア |
901万円超 |
|
イ |
600万円超~901万円以下 |
|
ウ |
210万円超~600万円以下 |
|
エ |
210万円以下(住民税非課税世帯を除く) |
|
オ |
住民税非課税世帯(注2) |
|
所得区分 |
自己負担限度額 |
|
|
3回目まで(注3) |
4回目以降(注4) |
|
|
ア |
252,600円+[(医療費-842,000円)×1%] |
140,100円 |
|
イ |
167,400円+[(医療費-558,000円)×1%] |
93,000円 |
|
ウ |
80,100円+[(医療費-267,000円)×1%] |
44,400円 |
|
エ |
57,600円 |
|
|
オ |
35,400円 |
24,600円 |
注1 所得区分ア~エにおける所得要件は、国民健康保険に加入している方それぞれの、所得控除前の総所得金額から基礎控除を引いた額の合計です。(基礎控除額は前年中の合計所得金額により変動します。)
注2 同一世帯の世帯主と、国民健康保険に加入している方全員が、住民税非課税であることです。
注3 ア~ウについて、[ ]内の計算は、0<[ ]の場合に適用されます。
注4 過去12か月間に、同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合に適用されます。
70歳以上75歳未満の方
70歳以上75歳未満の方は、限度額適用認定証をお持ちでない場合でも、資格確認書に記載の一部負担金の割合が2割の方は所得区分「一般」、3割の方は所得区分「現役並み所得者3」の自己負担限度額で計算されますが、所得区分「低所得者1」「低所得者2」「現役並み所得者1」「現役並み所得者2」に該当する場合は、申請することで限度額適用認定証が発行され、さらに低い自己負担限度額となります。
各所得区分の所得要件と自己負担限度額については以下のとおりです。
|
所得区分 |
所得要件 |
|
現役並み所得者3 |
同一世帯の70歳以上75歳未満で国民健康保険に加入している方の住民税課税所得(注1)が690万円以上 |
|
現役並み所得者2 |
同一世帯の70歳以上75歳未満で国民健康保険に加入している方の住民税課税所得(注1)が380万円以上690万円未満 |
|
現役並み所得者1 |
同一世帯の70歳以上75歳未満で国民健康保険に加入している方の住民税課税所得(注1)が145万円以上380万円未満 |
|
一般 |
低所得者1・2、現役並み所得者1・2・3以外の人 |
|
低所得者2 |
低所得者1の該当者を除く、住民税非課税世帯(注2) |
|
低所得者1 |
住民税非課税世帯(注2)かつ、その世帯の全員の所得が0円 |
|
所得区分 |
自己負担限度額(注3) |
|
|
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
|
|
現役並み所得者3 |
252,600円+[(医療費-842,000円)×1%] 【4回目以降(注4)140,100円】 |
|
|
現役並み所得者2 |
167,400円+[(医療費-558,000円)×1%] 【4回目以降(注4)93,000円】 |
|
|
現役並み所得者1 |
80,100円+[(医療費-267,000円)×1%] 【4回目以降(注4)44,400円】 |
|
|
一般 |
18,000円 |
57,600円 【4回目以降(注4)44,400円】 |
|
低所得者2 |
8,000円 |
24,600円 |
|
低所得者1 |
15,000円 |
|
注1 住民税課税所得とは、総所得金額から所得控除と調整控除、基礎控除を引いた額です。
注2 同一世帯の世帯主と、国民健康保険に加入している方全員が、住民税非課税であることです。
注3 現役並み所得者1~3について、[ ]内の計算は、0<[ ]の場合に適用されます。
注4 過去12か月間に、同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合に適用されます。
長期入院に該当する場合
所得区分「オ」または「低所得者2」に該当される方は、過去1年間の入院日数が90日以上になる場合、長期入院となることを申請することで、申請日から入院時の食事代が減額となります。(詳しくは、関連リンクより入院時の食事代のページをご覧ください。)
※入院日数とは所得区分が減額対象期間の合計日数です。国民健康保険以外で過去1年間内に入院がある場合は通算できます。その場合は食事代が減額対象であることを確認できる書類が必要です。
申請に必要なもの(マイナ保険証であれば申請は不要)
次のものをご用意のうえ、市役所7番窓口で申請してください。
・来庁される方のご本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
来庁される方が別世帯の場合、委任状が必要です。(成年後見人の方は、成年後見人の登記事項証明書があれば、委任状は必要ありません。)
郵便でも申請できます。
・限度額適用認定申請書(郵便用)(Wordファイル:26.4KB)
郵便申請の場合、世帯主の方が申請してください。
注意事項
・限度額適用認定証は発行された月から有効となります。発行月以前のものにつきましては、遡って適用されません。
・発行された月であっても、限度額適用認定証を提示前に医療機関等への支払いが終わっているものは適用されません。
・国民健康保険税に未納がある場合や、所得が未申告の場合、限度額適用認定証は発行されません。
・同じ月で、2以上の医療機関等を受診された場合は高額療養費の支給対象となる場合があります。(詳細については、関連リンクより高額療養費のページをご覧ください。)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
医療保健課
〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1339(医療保険係)
ファクス:076-475-1245
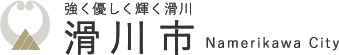



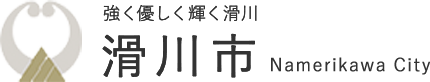




更新日:2025年08月01日