滑川市指定文化財(建造物・絵画・彫刻・工芸品)
建造物
養照寺本陣

養照寺上段の間
江戸時代、街道を往還する大名などの宿泊や休憩に用いられた施設を本陣という。本陣は主に大町の桐沢家が務めていたため、養照寺は主に脇本陣(本陣の予備施設)として利用されたが、度重なる火災で桐沢家が本陣の維持管理に支障をきたすと、天保13年(1842)からは養照寺が本陣となって、以後は瀬羽町の小泉屋とともに務めた。
本陣は御居間(上段の間)・鞘之間・白書院・黒書院・瀧之間(御次間)・桜之間(中間)などからなり、このうち藩主が利用した御居間(上段の間)は、「養照寺本陣(上段の間)」として、昭和57年(1982)に滑川市指定文化財に指定された。
その後、平成27年(2015)に本陣の測量調査が行われると、御居間(上段の間)を含めた本陣全体が、ほとんど当初のまま残っていることが新たに判明したため、令和3年3月に各部屋等の追加指定を行うとともに、「養照寺本陣」へと名称変更を行った。
なお県内の旧加賀・富山藩領の内、残存している本陣は、養照寺、寺林家(射水市)、伊東家(朝日町)のみであるが、江戸時代後期の本陣の姿を、ほぼ完全な状態で保った建物は養照寺のみとなっている。
所在地
滑川市領家町540
所有者・管理者等
養照寺
岩城家住宅

岩城家
野尻村の肝煎(きもいり)(村の代表)を務めた岩城家10代伝平が天保3年(1832)に建築したもの。現在は東福寺野自然公園内に移築されている。
間口11間半(約20.9m)、奥行5間半(約10m)、延べ面積68.1坪(225.2平方メートル)。茅葺(かやぶき)入母屋(いりもや)造り。県東部の間取りの特徴である「広間型」を基本とし、さらに奥座敷や控えの間を持つなど、接客空間が発達している。
広間は間口3間1尺、奥行3間半と大きく、太い梁を井桁状に組んだ「ワクノウチ」と呼ばれる構造になっている。柱や梁は上質の木材を使用し、堅牢で丁寧な造りがなされている。江戸時代後期の村役人屋敷の特徴をよく残している。
所在地
滑川市東福寺野不水掛41
所有者・管理者等
滑川市
絵画
釈迦三尊(三幅図)

釈迦三尊(三幅図)
(左 文殊菩薩、中 釈迦如来、右 普賢菩薩)
室町時代中期の作とされる三幅図は、釈迦如来を中心として、左に文殊菩薩、右に普賢菩薩を配した三尊形式をなし、徳城寺に寺宝として伝わったものである。
本尊の釈迦如来に比べ、脇侍との間には明らかな描法の違いが見られる。この三幅図は同一の時期に同一の作者によって描かれたものではなく、脇侍は後世になって本尊に合わせて描かれたものと推測される。絹本着色。
所在地
滑川市四間町598
所有者・管理者等
徳城寺
彫刻
神農坐像

神農坐像
この坐像は滑川の配置薬業者が所有していたもので、蓬髪(ほうはつ)の頭部には2 本の角を有し、面相は繊細な彫りで能面を思わせるような独特な仕上がりになっており、室町時代の作と推定されている。坐像背面に作者名と思しき「雲閣」との墨書があるが、作者の詳細は不明。
神農とは中国古代の伝説上の王で、人々に耕作を教えたため農業の神とされる一方、自ら草木を味わい薬草を見つけたため医療の神ともされた。
売薬業関係者には、薬の神として信仰されており、滑川では毎年1 月8 日、床の間に神農や懸場帳などを供え、商売繁盛と家内安全を祈願している。檜材、寄木造、黒漆塗。
所在地
滑川市開676
所有者・管理者等
滑川市立博物館
右大臣・左大臣、狛犬(対)
加積神社の社宝である左大臣・右大臣と一対の狛犬の由緒は定かではないが、狛犬の素朴で躍動感の見られない形状から鎌倉時代の作と推定されている。
右大臣の右目と喉元には、いつのものかは分からないが鉄釘が打たれており、この像に釘を打って強い願をかけた人物がいたのかもしれない。また、願いを聞き入れられなかった村人によって左腕を切り落とされたという伝承も残されている。杉材、一木造。

左大臣、右大臣

狛犬(左)、狛犬(右)
所在地
滑川市上小泉1362
所有者・管理者等
加積神社
帝釈天

帝釈天
この帝釈天は金の鍍金が施された青銅製で、室町時代の中国(明朝)で製作されたと推定されている。
由来書によると、文政期(1818~30)頃、堀江出身で摂津国在住の鯛喜という人物の夢枕に帝釈天が立ち、立山信仰の盛んな堀江に安置されることを望んだ。鯛喜が夢のお告げに従って探すとこの帝釈天が見つかり、そのため堀江に祀られて篤く信仰されたと伝わっている。
この帝釈天は旧立山道沿いの交観橋近くの地蔵堂に安置され、毎年8 月24 日の地蔵祭りでご開帳されてきたが、現在は滑川市立博物館において管理されている。
所在地
滑川市開676
所有者・管理者等
滑川市立博物館
釈迦如来坐像

釈迦如来坐像
釈迦如来は、様々なこの世の苦しみに悩んでいる人々を貴賤の区別なく等しく救済することを使命としている。
光明寺の本尊である穏やかな表情をたたえた宋風の釈迦如来坐像は、室町時代の作と推定されている。螺髪(らほつ)は大きく、肉髻(にっけい)にはメノウが埋め込まれ、彩色され金箔押の坐像となっている。蓮華座の上で定印(じょういん)といわれる印を結んだ様子は、釈迦が菩提樹の下で瞑想に入った時の姿である。
この坐像は、元は黄梅寺釈迦堂の本尊と伝わっており、現在、光明寺が建っている上梅沢城館跡が黄梅寺のあった場所と推察される。
杉材、寄木造、麻布張り彩色金箔押し。
所在地
滑川市上梅沢340
所有者・管理者等
光明寺
工芸品
加積雪嶋神社「みこし」

岩城庄之丈が製作した「みこし」
東本願寺再建工事の建築肝煎役などを務めた滑川の堂宮大工・岩城庄之丈により、京都伏見稲荷の神輿を参考に製作されたもので、明治23 年(1890)に納められた。天蓋(てんがい)は丸屋根八角型黒漆塗りで欅一本からの刳り出し、胴部は八角型金箔塗り、下部の八面に神猿を配し、四面の四神は透かし彫りの技法で装飾が施されている。前後左右の門は彫刻飾り戸付き、朱塗り欄干と鳥居付き等、技巧を凝らした美術工芸品である。総重量は450kg 程度といわれており、かつては屈強な男たちによって担がれていたが、現在では神輿車に乗せて巡行している。
所在地
滑川市加島町2050
所有者・管理者等
加積雪嶋神社氏子会
梵鐘

梵鐘
徳城寺の梵鐘は、室町時代中期以前に制作されたものと伝わる。しかし、松倉城の合図鐘であったとする説や、制作年が明記されている専長寺の梵鐘と、撞座つきざの文様や12 弁の菊蕾形の乳頭を持つなど類似点が見られることから、17 世紀後半から18 世紀初頭頃とする説もある。制作年代に諸説があり、また明治初年の廃仏毀釈や太平洋戦争時の金属強制拠出などをくぐり抜けてきたのも名鐘ゆえのことと考えられよう。
現在は、人間国宝の故金森映井智氏が制作したものが用いられており、この梵鐘は徳城寺の記念室に展示されている。
所在地
滑川市四間町598
所有者・管理者等
徳城寺
この記事に関するお問い合わせ先
生涯学習・スポーツ課
〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1483
ファクス:076-475-9320
メールでのお問い合わせはこちら
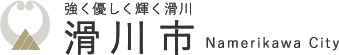



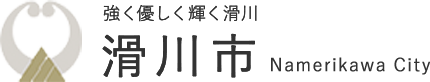




更新日:2023年04月01日