生活に困っている方へ…生活保護や生活困窮者自立支援について
様々な事情で生活が苦しくなってしまうことがあります。そのような際は福祉事務所(市役所福祉課)にご相談ください。生活保護をはじめとする様々な社会的セーフティーネットの利活用など、問題解決のための方策を相談者様と一緒に考えます。
生活について、心配ごとやお困りごとなどがあれば福祉事務所(市役所福祉課)の担当員や地区の民生委員にご相談ください。福祉事務所職員、民生委員には守秘義務があり、個人の秘密は固く守られますので、どうぞ安心してご相談ください。
生活保護について(国の制度 昭和25年創設)
資産や能力を活用しても生活に困っている方に対し、困っている程度に応じて必要な援助を行い、「健康で文化的な最低限度の生活」を保障すると共に、自立した生活を送れるよう手助けする制度です。日本国憲法第25条の「生存権」の理念に基づき、生活保護法で定められています。
○日本国憲法第25条第1項 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
生活保護とは
生活に困っているすべての人に対し、その困っている程度に応じて必要な援助を行い、最低限度の生活を保障するとともに、自分で生活できるよう手助けする制度です。意志があれば誰でも申請できます。気軽に相談してください。
調査内容と制度について
●生活保護と資産の関係
生活保護が申請されると、銀行や生命保険会社などへ資産調査を行います。預貯金、生命保険、土地家屋、自動車、高価な貴金属など売却や活用が可能な資産がある場合には、その資産を売却して最低生活費に充てていただくこともあります。
ただし、居住用の不動産は原則として保有が認められます。また、障害のある方の通院など、個別の事情によっては、自動車やオートバイの保有が認められる場合もあります。貯蓄性が高いものや保険料が高いものでない場合、生命保険、学資保険の保有が認められることもあります。
●能力の活用
働ける能力のある方は、その能力に応じて働く必要があります。ただし、病気や障害、その他の理由で働けない方は、その問題解決を優先とします。
●扶養義務について
親、子ども、兄弟姉妹などの民法上の扶養義務のある方から援助を受けることができる場合は受けてください。ただし、親族の扶養は、可能な範囲の援助を行うものであり、援助可能な親族がいることで保護の利用ができないということにはなりません。
親族から仕送りや養育費を受け取る場合には、収入として認定しますので、親族の方に可能な範囲での援助についてお伺いすることがあります。ただし、長期にわたり連絡を取っていない場合や、DV(家庭内暴力)、虐待など特別な事情がある場合には、親族への照会を見合わせることもあります。事前に相談してください。
●ほかの制度の活用
生活保護以外にも年金、各種手当、医療助成、社会保障制度など、生活を支えるための様々な公的な制度があります。活用が可能な制度がある場合には、それらを優先して活用していただきます。
生活保護の内容
世帯を単位として、その世帯の最低生活費の額と世帯全員の収入額を比較し、不足する場合にその不足する額が保護費として支給されます。
保護の種類は、次の8つの扶助があり、生活状態に応じて必要な援助が受けられます。
1.生活扶助 日常の暮らしに必要な費用(衣・食)
2.住宅扶助 家賃及び住宅の維持のために必要な費用
3.介護扶助 介護サービスなどの費用
4.教育扶助 義務教育に必要な費用
5.医療扶助 病気やけがの治療に必要な費用
6.出産扶助 お産をするのに必要な費用
7.生業扶助 手に職をつけたり、仕事につくための費用
8.葬祭扶助 葬式のとき必要な費用
意思があれば誰でも申請できます。お気軽にご相談ください。
生活保護の申請は、国民の権利です。意志があれば誰でも申請できます。生活にお困りの方はお気軽にご相談ください。生活保護のあらましを分かりやすく説明した「生活保護のしおり」がありますので、ぜひご覧ください。
滑川市「生活保護のしおり」PDF (PDFファイル: 1.3MB)
生活困窮者自立支援について(国の制度 平成25年創設)
生活困窮者に対し、自立相談支援事業の実施、住居確保給付金の支給その他の支援を行うことにより、生活保護に至る前の段階で自立の促進を図ることを目的とするものです。
生活困窮者自立支援の対象となるのは
現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある方です。
生活困窮者自立支援の内容
本市で実施している支援事業は次のとおりです。
○自立相談支援事業:就労など、自立に向けた包括的な相談支援、各種の支援利用のプランニング
○住居確保給付金:離職等により住宅を失った生活困窮者等への住居確保のための金銭給付(有期)
○就労準備支援事業:就労に必要な訓練の実施
○家計改善支援事業:家計管理能力を高めるための支援の実施
○一時生活支援事業:住居のない生活困窮者への宿泊場所や衣食の提供(有期)
なお、事業の実施については、富山県社会福祉協議会(東部生活自立支援センター)等に委託しています。
生活福祉資金の貸付け(国・県の制度 昭和38年創設)
低所得者に対し、経済的自立と生活意欲の促進を図るため、次の種類の生活福祉資金の貸付制度があり、滑川市社会福祉協議会でその事務を行っています。
貸付対象
(1)低所得世帯 ※所得制限あり
資金の貸付にあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、独立自活に必要な資金の融資を他から受けることが困難であると認められる世帯(所得制限あり)
(2)障がい者世帯
身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方の属する世帯、障害者総合支援法によるサービスを利用している方の属する世帯
(3)高齢者世帯 ※所得制限あり
日常生活上療養または介護を要する65歳以上の高齢者の属する世帯(所得制限あり)
留意事項
○「世帯」に対する貸付です。
生活福祉資金は「個人」ではなく「世帯」を単位として貸付けを行います。相談者ご本人だけでなく、世帯員全員の就労・就学状況、健康状態、収入や負債等について確認させていただき、生活の立て直しに向けた適切な支援を検討します。
○「世帯の自立につながる」と判断される場合に貸付を行います。
本制度は「給付」ではなく「貸付」であることから、償還(返済)していただく必要があります。貸付金の償還が見込めない場合には、世帯にとって「借金を負う」という新たな負担につながりますので、貸付を行うことはできません。
○社会福祉協議会や民生委員等による継続的な相談支援を行います。
本制度は、単なる金銭の貸付ではなく、世帯の安定や生活の立て直しを図ることを目的にしています。そのため、貸付後もお住まいの地域の民生委員や滑川市社会福祉協議会、生活困窮者自立支援法に基づく相談支援機関等が継続して生活状況を確認し、必要に応じて相談支援を行います。
○他の貸付制度や公的支援等を優先してご利用いただきます。
本制度は、必要な資金の貸付を他から受けることができない世帯が対象です。そのため、母子父子寡婦福祉資金や日本学生支援機構の奨学金、日本政策金融公庫、その他の金融機関等からの借入れが可能な場合は、そちらをご利用いただくことになります。また、給付制度や助成制度の利用、家計の見直し、分割払い等、貸付以外の方法が考えられる場合にはそちらを優先していただきます。
○事後申請は貸付対象外です。
すでに発注、購入、着工、支払い済みの費用は賃付の対象となりません。ただし、福祉費の療養関係経費、葬儀費用については、事前申請が困難な場合、支払い前であれば貸付対象となることがあります。
○他の債務の返済資金に充当する場合はお貸しできません。
○審査によって、借入金額が減額される場合や貸付が不承認となる場合があります。
貸付対象とならない世帯であっても、他施策・他機関と連携して相談支援を行います。
○虚偽の申請や不正な手段により貸付を受けた場合は、貸し付けた金額を即時にご返済いただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1377(社会福祉係)
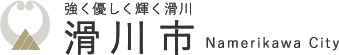



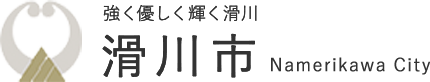




更新日:2025年03月03日